2020年NHK大河「麒麟が来る」では、土岐頼芸役を尾見としのりさんが演じます。
なるほど優美な雰囲気の、どちらかというと公家よりの武者のイメージがありますね。
それもそのはずで、土岐家のような守護は、応仁の乱以前は京に住んでいることが多く、そこで身に付けた京文化を美濃に伝え自分たちもそれに習ってきたのです。
特に土岐頼芸を始め、頼忠、富景、頼高らが描いた「鷹の図」は、土岐の鷹として高い評価を得ています。
それ以外にも和歌・連歌・漢詩などの文の領域、猿楽・舞・絵画などの芸術・芸能面に深い造詣を持つ一族でした。
しかし決して武をおろそかにしていたわけではなく、頼芸も実は勇猛な武将だったと伝わっています。

土岐頼芸の一生
文亀2年(1502年)に美濃の守護、土岐政房の次男として生まれました。
当時の美濃は守護代斎藤家が波乱含みの状況にありました。
斉藤利国が戦死し守護代斎藤家が衰退するなか、頭角を現してきたのが長井家でした。
この長井家に斎藤道三の父・西村勘九郎正利がおり暗躍していたということです。
詳しくは斎藤道三を紹介したこちらのページを参考にしてください。
時を同じくして守護代土岐家にも暗雲が漂っていました。
頼芸の父・政房には長男の頼武がいましたが、正房は頼芸を溺愛するあまり頼武を廃嫡し頼芸を後継者にしようとしました。
父正房や勢いをつけてきた長井長弘らが後ろ盾となり頼芸を擁立。
一方、兄頼武を支持するのは衰退気味の守護代斎藤利良ら。
双方が家督争いで衝突し、1517年合戦となりましたが頼芸はこの時敗れています。
翌1518年は頼芸が勝利し兄を越前に追放。
1519年朝倉氏の支持を得た兄頼武が美濃に侵攻し圧勝。
頼武が美濃守護を拝命し、これで決着がついたかのようにみえました。
1530年、頼芸がまたまた挙兵しました。
兄を再び越前国に追放し、「濃州太守」と呼ばれて実質的な守護となりました。
その後、後ろ盾であった斎藤長弘、道三の父らが相次いで死去したため、長井規秀(後の斎藤道三)を重用し勢力保持をはかったといわれています。
これが結果的に道三の国盗りに繋がっていきます。
天文4年(1535年)6月、父の17回忌を執り行い、自らの正統性を国内に宣言したためまたも戦火が美濃中に広がりました。
兄の跡を継いだ甥・頼純と対立が激化したのです。
甥の頼純に加担したのが、朝倉氏・六角氏などの有力な武将たちでした。
同年7月1日、新たな守護所であった枝広館が長良川大洪水で流され、稲葉山の麓に移ることになります。
この水害も土岐氏の経済力の基盤を揺るがす惨事だったといわれています。
同年6月22日、第12代将軍・足利義晴の執奏により、修理大夫に任官。
翌天文5年(1536年)、勅許により美濃守に遷任して正式に守護の座に就きました。
六角氏の娘を娶り、甥・頼純と和睦し、やっと美濃が落ち着いたと思われたのですが——-。
道三が頼芸の弟・頼満を毒殺する事件が起こったため、道三との対立が色濃くなっていきます。
1542年、頼芸は子の頼次ともども道三により尾張国へ追放されてしまいました。

この後頼芸は凝りもせず守護代復帰にやっきになります。
朝倉氏の庇護下にいた頼純と連帯し一時的に守護に復職しました。
しかし直後の1546年、朝倉氏と斎藤道三の和睦が成立し、その条件が頼芸の守護退任だったため、地位を頼純に渡しています。
1548年には道三と織田信秀も和睦。
これで後ろ盾を全て失った土岐頼芸は1552年、ふたたび道三に追放されました。
近江国・常陸国・上野国と渡り歩き、甲斐の武田氏に身を寄せてる頃病気で失明したとあります。
織田信長の甲州征伐の際、武田氏に庇護されていた頼芸が発見されました。
頼芸の旧臣であり織田家家臣だった稲葉一鉄の計らいで美濃国に戻り、半年後1582年に死去しています。
余談ですが、この稲葉一鉄いう武人は頑固一徹の語源になったいう人で、本能寺の変直後には明智光秀の子供を逃がし匿った人物ともいわれています。
土岐頼芸の墓は、揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼「法雲寺」にあります。
元々墓は川西の山麓にありましたが、昭和49年現在の法雲寺に移されています。







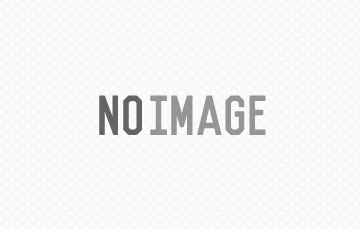



コメントを残す