2020年NHK大河ドラマ「麒麟がくる」明智光秀ゆかりの地、京都編4回目です。
どこまで紹介しようかと悩みつつも、出来るだけ微細な場所まで発掘しようと意気込んでいます。
[su_highlight background=”#d065ce” color=”#fefdfd”]明智光秀ゆかりの地㏌京都を、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの記事はこちらへ ☟☟ [/su_highlight]

友渕城址
丹波平定の拠点として光秀が築いた城です。
友渕山に築城された城で一部現存しているようです。
が住所がなくて場所のご紹介ができません。
興味のある方は、こちらのPDFを参考にしてください。
山崎光秀本陣跡
「山崎の合戦」で明智光秀が本陣をおいたとされる「御坊塚」。
以前は境野1号墳とされていましたが、現在は恵解山古墳(いげのやまこふん)とする説が有力となっています。
2011年(平成23年)に長岡京市埋蔵文化財センターが発表したところによると、火繩銃の玉や、兵が駐屯するために古墳を平らに整形した曲輪の跡が見つかったほか、幅4~5m、深さ約2mで、49mにわたる堀跡が確認されています。
「堀の形状も全国の陣城の事例と似ており、遺物が少ないのも急ごしらえで造る陣城の特徴。平野部にぽつりとある恵解山古墳は戦略上も陣地を置くのに適している。堀が東西にも伸びて古墳を囲んでいた可能性もある」と滋賀県立大学の中井均准教授はコメントしています。
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m16!1m12!1m3!1d3271.6810333021053!2d135.69524826458144!3d34.914453279249!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!2m1!1z5oG16Kej5bGx5Y-k5aKz!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1569643919890!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450]明智風呂
光秀は風呂好きでした。
当時の風呂は湯船のある現在のスタイルではなく、サウナのような蒸し風呂だったのです。
京都時代の朋友、吉田兼見宅を訪れては風呂を所望したと兼見日記に記載されています。
この明智風呂は、1587年塔頭大領院(現在は妙心寺)の蜜宗和尚が光秀を弔うために造ったものです。
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3267.3167786787576!2d135.71830001458486!3d35.023804273353775!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x6001079b12de9469%3A0xa45e5908a70f426!2z5aaZ5b-D5a-6!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1569644507768!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450]山崎の戦いで羽柴秀吉(豊臣秀吉)に敗れ、近江の坂本城へ逃れる途中、小栗栖の竹藪で農民に襲われて自刃。
光秀は家来に知恩院で灰にしろと命じたそうですが、光秀の首を落とし運ぶ途中で夜が明けたため、この地に首を埋めたと伝えられています。
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3267.9379536054334!2d135.77840421458433!3d35.00825827419291!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x600108e80778e465%3A0x18644e8d2a5d65aa!2z5piO5pm65YWJ56eA6aaW5aGa!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1569644761387!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450]黒井城址
丹波平定において、光秀が一番苦しめられた丹波の赤鬼・赤井直正の居城です。
黒井城とは、本来猪ノ口山系と呼ばれる、約120ヘクタールにも及ぶ広大な山地全体が城の領域です。
山中の至るところに曲輪や土塁、堀切などの防御施設があります。
さらにこの広大な黒井城と連携する支城や砦が、約1kmごとに張りめぐらされており、防御体制としては盤石でした。
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m16!1m12!1m3!1d6336.710929004139!2d135.09845033076917!3d35.17668348852433!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!2m1!1z6buS5LqV5Z-O5Z2A!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1569645820848!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450]八上城址
八上城は丹波富士とも呼ばれる高城山に築かれた山城で、波多野秀治の居城として知られています。
光秀は長い時間をかけて兵糧攻めにして落としています。
また人質として差し出した光秀の母が、この城で殺されたという伝説があり、磔の松も残っています。
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3265.79405964176!2d135.25389441458603!3d35.06188757129703!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60006bae944f9e45%3A0x2c81b1e197fe71be!2z5YWr5LiK5Z-O6Leh!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1569646070912!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450]高山寺
京都府右京区にある有名な高山寺とは違います。
こちらは丹波市氷上町にあります。
信長の命により、光秀はここのあった釣り鐘を下ろし、柏原八幡宮にある仮本陣に運んだと伝わっています。
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3260.880199135205!2d135.02683731458976!3d35.18453836465991!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x6000071a39401c3d%3A0x333fd0b8c66aa63a!2z6auY5bGx5a-6!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1569646493573!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450]金山城
金山城は丹波制圧にのりだした明智光秀によって築かれた城です。
八上城と黒井城の連携を断つことを目的に造られて戦術的な城だったため、丹波平定後、天正10年頃には戦略的に不要となった金山城は廃城となったと考えられています。
現在は土塁や石垣が一部残るだけですが、本丸からは八上城と黒井城を眺めることができます。
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d8100.815528041422!2d139.36759116897753!3d36.31689427962066!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x601f201230472b13%3A0xb3462335a52a9441!2z6YeR5bGx5Z-OKOaWsOeUsOmHkeWxseWfjinot6E!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1569646830020!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450]玉雲寺
かつては滝つぼのすぐ脇に建っていたそうです。
しかし1579年の明智光秀の市森城攻撃によって寺の建物や宝物はほとんど焼失してしまいました。
現在の境内・本堂・庫裏は光秀が禅氏の道徳を尊崇し、翌年に光秀自身が再興したものです。
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3262.6436052140193!2d135.43164931458833!3d35.14056636704162!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60004639d097cc1d%3A0xc4ce575be44e3df8!2z546J6Zuy5a-6!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1569647065405!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450]




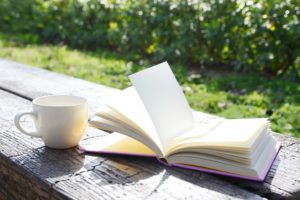





コメントを残す