明智光秀は滋賀県の生まれ!
滋賀県ではそんな声が上がっているそうです。
岐阜県多賀町こそ光秀が生まれた場所という説ですが、教育委員会も強烈にプッシュしているそうですから、思いのほか熱い論争が起こるかもしれません。
この説の由来は、県文化財保護課主幹の井上優さんが、江戸初期に刊行した近江の地誌「淡海温故録」に、「犬上郡左目」(現多賀町佐目)に「明智十左衛門が居住していた」とする記述を紹介したことがきっかけです。
明智という名前は特に珍しい姓ではなく、十兵衛も然りです。
しかし明智光秀の出生については、まだまだ謎が多いのが実情。
現在大勢を占める岐阜説から、滋賀説が有力といわれる日がきても不思議ではありません。
では滋賀県にある明智光秀ゆかりの地をご紹介しましょうご♪

高島市の大溝城(おおみぞじょう)
1579年津田信澄が織田信長から高島郡を拝領し、明智光秀の縄張りで大溝城が築かれました。
津田信澄は明智光秀の娘を正室にしていたので、本能寺の変の後に殺害されています。
その後城主は目まぐるしく変わりましたが、一国一城令の対象となり、三の丸を残して大溝城を破壊してしまいました。
残した三の丸に陣屋を築く、大溝陣屋(おおみぞじんや)として明治維新を迎えています。
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3256.5441435715984!2d136.01073451459303!3d35.292458558803695!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60019a674f3de7f9%3A0xd4407d4e525be24d!2z5aSn5rqd5Z-O6Leh!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1566821739574!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450]今堅田城
浅井・朝倉軍が織田信長と戦った際、今堅田城に甲賀武士団の磯谷新右衛門を主将として守備させました。
これを湖側から攻め落としたのが、明智光秀・丹羽長秀らでした。
出来島あたりが今堅田城(いまかたた)と云われていますが詳細は不明です。
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3263.523486066313!2d135.92415171458765!3d35.118607868230114!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60017519ac89abbd%3A0x28f3a6c9b557cfbe!2z5LuK5aCF55Sw5Z-O!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1566821964040!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450]西教寺
比叡山延暦寺焼き討ちの際、西教寺も焼け落ちています。
その後この地いったいを治めたのが明智光秀です。
光秀が築いた坂本城と西教寺は、距離的に近かったこともあり、互いに良い関係にあり、寺の復興にも光秀の援助があったと推定されています。
光秀が戦死した部下の供養のため、西教寺に供養米を寄進した際の寄進状が寺に現存していることでも有名です。
また、境内には光秀の供養塔や光秀一族の墓もあります。
総門は坂本城城門を移築したもので、鐘楼堂の鐘は陣鐘です。
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3265.006839037812!2d135.86386041458667!3d35.08156187023366!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60010af55f09f7c1%3A0xe22ec60e34df3968!2z6KW_5pWZ5a-6!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1566822264001!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450]聖衆来迎寺(しょうじゅらいこうじ)
旧坂本城の門を移したという表門があります。
この寺は比叡山延暦寺の焼き討ちで焼き討ちを免れた稀有な寺です。
そのため当時の文化財が多く現存していることで知られています。
ただし、1662年の大地震をはじめとする災害によって堂舎はたびたび破損し、光秀が活躍した時代の建物は残っていません。
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3265.3679608640396!2d135.88403371458617!3d35.0725378707215!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60010b203ecea891%3A0xf89016386684805a!2z6IGW6KGG5p2l6L-O5a-6!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1566822555168!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450]盛安寺
こちらも比叡山焼き討ちの際に焼失し一時衰退した時期もありましたが、光秀の庇護により再興されています。
境内に入ると二階建ての太鼓楼という建物や、明智光秀の供養塔などがあります。
太鼓楼の壁には、「明智公顕彰 佛の城太鼓楼 法王院盛安寺」と記された駒札が柱に懸けてあります。
リーフレットには、「天正年間ある夜、当時の『暁の鼓』(夜明けを知らせる太鼓)を打って敵の急襲を知らせた恩賞として、光秀公より庄田八石(太鼓田)を賜る」と説明が記されています。
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3265.9437513433923!2d135.86621631458587!3d35.05814537149919!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60010b064ad9edd5%3A0x615d897e12953753!2z55ub5a6J5a-6!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1566822881543!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450]宇佐山城
比叡山焼き討ちの際に、光秀が拠点とした城です。
築城は1570年、織田信長が家臣の森可成に命じて建てた城です。
森可成は信長が非常に信頼していた家臣だったようですが、比叡山焼き討ちの前、浅井・朝倉との戦いで戦死。
戦死した森可成の遺体を夜中に極秘で運び埋葬したのが聖衆来迎寺でした。
そのため焼き討ちから免れたのではないかと言われています。
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d52255.05547892164!2d135.83338534729916!3d35.05821497072271!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60010beb581200e1%3A0xcadde0a16c284697!2z5a6H5L2Q5bGx5Z-O6Leh!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1566823241003!5m2!1sja!2sjp&w=600&h=450]




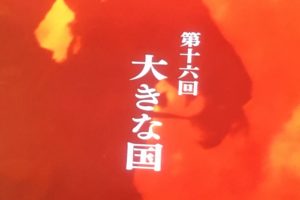






コメントを残す